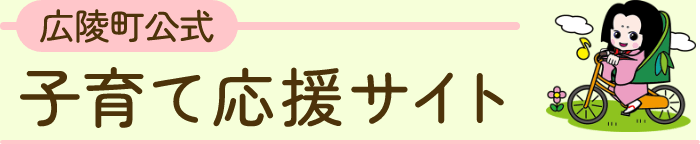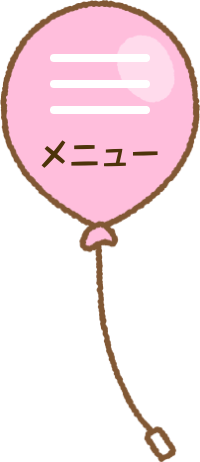各種補助金等について
- 更新日:
- ID:7348
- 一般不妊治療費助成
- 生殖補助医療(不妊治療)助成事業
- 妊娠判定料受診料の助成
- 妊婦健康診査費用の助成
- 妊婦のための支援給付
- 新生児聴覚検査費用の助成
- 産婦健康診査費用の助成
- 1か月児健康診査費用の助成
- 奈良県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業
- 骨髄移植等による予防接種再接種費用助成
- 子ども医療
- ベビーシッター利用支援事業
- 広陵町子育て短期支援事業
- 児童扶養手当
- 特別児童扶養手当
- 児童手当
- 私学助成幼稚園の副食費無償化(補足給付事業)
- 保育料・一時預かり事業利用料・病児、病後児保育事業利用料の無償化
- 交通遺児等援護事業
- 就学援助制度
- 就学援助(新入学学用品費)の入学前支給 ※受付期間:令和8年1月9日(金)~令和8年1月30日(金)
- 広陵町小・中学校多子世帯給食費支援金
一般不妊治療費助成
不妊に悩む夫婦の経済的な負担の軽減を図るために、一般不妊治療を受けている夫婦に対して、費用の一部(1年度につき1回、上限5万円)を助成します。
詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。
生殖補助医療(不妊治療)助成事業
不妊治療のうち、体外受精及び顕微鏡受精(以下、生殖補助医療)並びにこれに併せて行われる先進医療に要する費用の一部を助成します。
詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。
妊娠判定料受診料の助成
住民税非課税世帯または生活保護世帯に属する女性に対し、妊娠判定検査に要する費用(1回7,000円を上限として1年度2回まで)を助成します。
詳しくは、下記のリンクをご覧ください。
妊婦健康診査費用の助成
妊娠の届出をした妊婦に母子健康手帳及び、妊婦健康診査受診券を交付します。妊婦健康診査受診券を利用することで、妊娠中の健康状態を定期的に確認するための健診費用の助成を受けることができます。
詳しくは、下記のリンクをご覧ください。
妊婦のための支援給付
新生児聴覚検査費用の助成
生後約28日以内に初めて受ける聴覚検査の費用(自動ABR:4,000円、OAE:1,500円を上限)を助成します。受診券は、妊婦健康診査受診券の綴りとともに交付します。
詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。
産婦健康診査費用の助成
産後2回分(おおよそ産後2週間前後、1か月前後)の産婦健康診査にかかる費用(1回、5,000円を上限)を助成します。受診券は、妊婦健康診査受診券の綴りとともに交付します。
詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。
1か月児健康診査費用の助成
出生後28日から41日までの乳児を対象に実施される、1か月児健康診査にかかる費用(6,000円を上限に1回まで)を助成します。受診券は、妊婦健康診査受診券の綴りとともに交付します。
詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。
奈良県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業
奈良県では、将来こどもを産み育てることを望む小児・AYA世代のがん患者等が、希望をもってがん治療等に取り組めるように、将来子どもを出産することができる可能性を温存するための妊孕性温存療法及び温存後生殖補助医療に要する費用の費用の一部を助成します。
※「AYA世代」とは、Adolescento and YoungAdult(思春期・若年成人)の頭文字をとったもので、おもに思春期(15歳)から30歳までの世代を指します。
詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。
奈良県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業について/奈良県公式ホームページ別ウィンドウで開く
骨髄移植等による予防接種再接種費用助成
骨髄移植、末梢血幹細胞移植及びさい帯血移植等の造血幹細胞移植又は抗がん剤治療等の化学療法(以下、骨髄移植等)により、定期予防接種で獲得した免疫の効果が低下または消失したと医師に判断され任意に再接種を受ける人に対し、再接種に要する費用の一部を助成します。
詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。
子ども医療
健康保険に加入している18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもに対し、1ヶ月単位で医療機関等に支払った保険適用の医療費自己負担額から一部負担金(加入の保険者から支給される場合の高額療養費及び付加給付金)を差し引いた額を給付します。
〈一部負担金〉
〇通院…1医療機関(レセプト)ごとに500円
〇入院…1医療機関(レセプト)ごとに1,000円(14日未満の場合は500円)
(注意)総合病院の場合は、医科・歯科ごとに一部負担金が発生します。
(注意)調剤薬局に一部負担金はありません。
詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。
ベビーシッター利用支援事業
就労の有無にかかわらず、ベビーシッターを利用した際の利用料(入会金、会費、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代等の実費等は含みません。)について、一部を助成します。
詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。
広陵町子育て短期支援事業
保護者の疾病などの理由により、家庭でお子さんを養育することが一時的に困難となった場合や、保護者が仕事で不在となる場合等、お子さんを保護することが必要な場合に、児童養護施設等でお子さんを一定期間養護・保護する制度です。
詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。
児童扶養手当
支給額(月額)
〇児童1人目 全部支給46,690円、一部支給11,000円から46,680円
〇児童2人目以降 全部支給11,030円、一部支給5,520円から11,020円
詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。
特別児童扶養手当
手当の額は児童の障がいの程度に応じて決まります。
手当の額(児童1人あたりの月額)
〇障がいの程度1級 56,800円
〇障がいの程度2級 37,830円
詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。
児童手当
〇満3歳未満第一子・第二子:月15,000円 第三子以降:月30,000円
〇満3歳から18歳になった最初の3月31日まで第一子・第二子:月10,000円 第三子以降:月30,000円
(注意)第1子、第2子、第3子の数え方は、22歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童や児童の兄姉の出生順です。
詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。
私学助成幼稚園の副食費無償化(補足給付事業)
私学助成幼稚園に通園する満3歳児から5歳児について、町民税の所得割課税額77,101円未満や多子世帯を対象に1人当たり月額4,900円を上限に、給食費のうち副食費の一部を町が補助します。年度のうち、前期(4月から8月)と後期(9月から3月)に分けて、申請の受付・支給を行います。
(注意)私学助成幼稚園:広陵町近辺だとハルナ幼稚園や片岡台幼稚園が対象の園となります。
(注意)副食費:ごはん・パン等の主食を除いたおかず・おやつ・牛乳・お茶等の食材料費
(注意)前期と後期で判定する所得の年が変わります。(前期:前々年の所得、後期:前年の所得)
詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。
保育料・一時預かり事業利用料・病児、病後児保育事業利用料の無償化
令和元年10月から、保育所、認定こども園、幼稚園(町外の一部幼稚園を除く)などを利用する主に3歳児から5歳児と住民税非課税世帯の0から2歳児については、保育料が無償(保護者の方が実費で負担する食材料費や教材費などを除く)となりました。
また、認可外保育施設や幼稚園の預かり保育の利用料についても、保育の必要性があると認定された方は、一定の基準額まで無償になりますが、施設の利用前にあらかじめ「子育てのための施設等利用給付」の申請が必要となりますのでご注意ください。
詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。
保育料・一時預かり事業利用料・病児、病後児保育事業利用料の無償化について | 広陵町
交通遺児等援護事業
交通災害又は自然災害により、父又は母等を失った児童の健全な育成及びその福祉の増進を目的として、激励金や入学祝金等の給付を行う事業です。
〇交通遺児等激励金
死亡より1年以内に申請が必要です。
給付額:遺児一人につき100,000円
〇交通遺児等入学祝金
小学校、中学校、高等学校入学時より1年以内に申請が必要です。
給付額:遺児一人につき50,000円
詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。
就学援助制度
経済的理由により小中学校への就学が困難な児童生徒の保護者の方に、学校でかかる費用の一部(学用品費や学校給食費など)を援助しています。
詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。
就学援助(新入学学用品費)の入学前支給 ※受付期間:令和8年1月9日(金)~令和8年1月30日(金)
広陵町では、令和8年4月に小学校・中学校に入学予定で、経済的な理由によって就学準備が困難なお子さんの保護者(生活保護世帯を除く)の方を対象に、申請に基づいて審査して、「新入学学用品費」を入学前に支給します。
詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。
広陵町小・中学校多子世帯給食費支援金
小学1年生から中学3年生までの児童生徒が3人以上いる世帯の3人目以降の給食費に対し、4,000円/月を支給します(要件あり)。
※対象となるお子様が広陵町立小学校・中学校に通われている場合、令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間は、小学校・中学校の給食が無償となるため、支給対象外となります。
詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。