“ふるさと納税”における寄附金控除について
- 更新日:
- ID:2177
ふるさと納税とは、出身地や全国すべての応援したい自治体に寄附することができる制度です。
テレビや雑誌で「ふるさと納税はお得!」という話を見聞きしますが、これはふるさと納税をすると、翌年の所得税や個人住民税から一定金額が控除されたうえ、寄附をした自治体から返礼品がもらえるからです。しかしながら、寄附額がすべて控除されるわけではありませんし、控除額の上限は寄附をする年の所得額によって変わってきます。また、所得税や個人住民税を納めていない方(非課税の方)は控除する税金がありません。税の軽減を受けようと考える方は、寄附金の限度額に注意が必要です。
制度の概要
- 自治体に2,000円を超える寄附を行った場合に、一定の上限まで所得税と個人住民税が控除されます。
- 寄附金控除を受けるためには、翌年に税務署で確定申告を行う必要があります。
- 給与所得者等は、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用すると確定申告が不要となります。
- 所得税については、寄附をした年分の所得から控除されます(所得控除)。
- 個人住民税については寄附をした年の翌年に課税される税額から控除されます(税額控除)。
ふるさと納税ワンストップ特例制度について
ふるさと納税による税の軽減を受けるためには、確定申告をする必要がありますが、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用すると、確定申告を行わなくても税の軽減を受けることができます。この適用を受けると、所得税の軽減相当額を含めて、ふるさと納税をした翌年の個人住民税からまとめて税額控除されます。ただし、この制度を利用するには下記の条件を満たしている方が対象となりますのでご注意ください。
特例の適用を受けることができる対象者
下記の1と2両方の条件を満たす方が対象となります。
- 申告をする必要のない方
給与所得者や年金所得者など確定申告の必要のない方。確定申告をしなければならない自営業者や、給与所得者や年金所得者の方でも医療費控除などで申告をする方、個人住民税申告をする方は対象になりません。また当初は申告をする予定がなく、特例の申請をされておられたとしても、後に申告をされた場合には特例適用を受けられなくなります。その際の申告時では、寄附金に関する申告もお忘れのないようご注意ください。 - ふるさと納税をする自治体数が5か所以下と見込まれる方
5か所以下の自治体に寄附する見込みであれば、特例適用を受けることができます。もし1年間の結果として6か所以上の寄附となってしまった場合には、ご自身で申告をする必要があります。同じ自治体に複数回寄附をした場合は1か所とカウントします。
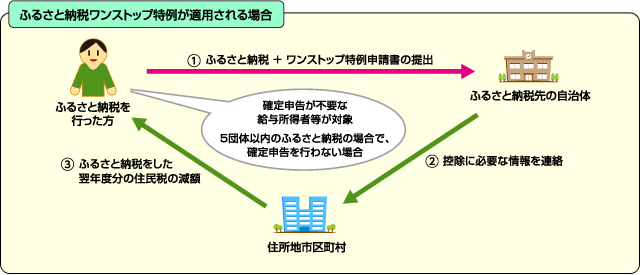
ワンストップ特例の仕組み
(注意)自治体によって申込手続きや申請書が異なることがありますので、ふるさと納税をする際にはふるさと納税先の自治体にお問い合わせください。
控除額の計算方法
- 所得税(所得控除)
所得控除額=(寄附金-2,000円)→税額に直すと、(所得控除額×所得税率)円が軽減されます。 - 個人住民税(税額控除)=下記(1)+(2)
(1)基本控除額=(寄附金-2,000円)×10%
(2)特例控除額=(寄附金-2,000円)×(90%-所得税率)
(補足)所得税の寄附金控除の控除対象寄附金は総所得金額等の40%が限度
(補足)個人住民税の基本控除の控除対象寄附金は総所得金額等の30%が限度
(補足)個人住民税の特例控除の控除対象寄附金は住民税所得割額の20%が限度
(補足)ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用される場合は、所得税寄附金控除額相当額を住民税の申告特例控除額として控除します。
ふるさと納税限度額の計算について
実際に寄附をするに当たり、実質寄附額が2,000円負担となる寄附金の限度額を計算してみましょう。
寄附する時点では、その年の所得税の課税所得金額や個人住民税の所得割額は確定していないので、計算式はあくまでも目安となります。参考に前年度の所得情報など(源泉徴収票や市町村民税・県民税税額納税決定通知書などを確認してください)で計算してみてください。
所得税の課税総所得金額 | 所得税率 | 上限額の計算式(課税総所得金額に応じた計算式です。) |
|---|---|---|
195万円以下 | 5% | 寄附金の目安金額=所得割額×23.558%+2千円 |
195万円超330万円以下 | 10% | 寄附金の目安金額=所得割額×25.065%+2千円 |
330万円超695万円以下 | 20% | 寄附金の目安金額=所得割額×28.743%+2千円 |
695万円超900万円以下 | 23% | 寄附金の目安金額=所得割額×30.067%+2千円 |
900万円超1,800万円以下 | 33% | 寄附金の目安金額=所得割額×35.519%+2千円 |
1,800万円超4,000万円以下 | 40% | 寄附金の目安金額=所得割額×40.683%+2千円 |
4,000万円超 | 45% | 寄附金の目安金額=所得割額×45.397%+2千円 |
所得税の課税総所得金額とは
国税である所得税の課税総所得金額により判定します。総所得金額から所得税における所得控除の合計額を控除した残額のことです。つまり所得税額を算出するため、税率をかける所得金額をいいます。確定申告書では「課税される所得金額」欄の額、源泉徴収票では「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を引いた額です。
個人住民税の所得割額とは
個人住民税の課税総所得金額に税率をかけて算出した税額(総所得金額等に係る所得割額と分離課税に係る所得割額の合計額)から調整控除額を控除した後の税額(住宅借入金等特別控除などの税額控除を引く前の税額)をいいます。これは市町村民税・県民税税額納税決定通知書(補足)の「市町村民税の所得割額」と「県民税の所得割額」の欄の合計額を見てください。
(補足)決定通知書は、給与から個人住民税が特別徴収されている場合、毎年6月分の給与明細を受け取る頃に、会社から受け取っていただけます。またご自身で金融機関などへの振込や口座振替していただいている普通徴収の方は6月10日前後に役場からご自宅宛てにお送りしております。
お問い合わせ
広陵町住民環境部税務課
電話: 0745-55-1001
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
